投資を始めたばかりの頃
「なんでこの銘柄、こんなに上下に動くの?」と戸惑った経験はありませんか?
私も最初は、ただ、「有名企業だから」や「今、上昇トレンドだから」曖昧な理由で株取引をしては含み損が出て疲れ切ってた頃。そんな時に出会ったのがチャート指標のひとつ「ヒストリカル・ボラティリティ(HV)」。
これを知ってからは、事前に“どれくらい振り回されそうか”を把握できるようになり、ストレスも激減しました。株価の「荒れ具合」が数値で見えるこの指標は、初心者こそ知っておきたい武器です。投資歴18年の私が、かみ砕いて分かりやすく解説します!
- ヒストリカル・ボラティリティの意味
- 計算方法と日数設定の違い
- 高ボラティリティ銘柄の特徴とリスク
- 実際のチャート上での使い方
- 投資判断への活かし方(NISA・FIRE戦略含む)
ヒストリカル・ボラティリティとは?
過去の値動きの“激しさ”を数値化したもの
ヒストリカル・ボラティリティ(Historical Volatility)は、一定期間の株価の変動幅から「その銘柄がどれくらい動きやすいか(不安定か)」を表す指標です。値動きが大きい=高ボラ、小さい=低ボラ。個人投資家の「ストレス耐性」にも影響する大事な視点です。

英語表記と略語
通称HV、プロもよく使う略語です。
ヒストリカル・ボラティリティは「Historical Volatility」と書き、略してHV(エイチブイ)と表現されます。アナリストのレポートや証券アプリのチャートでもHVという記載があれば、それは過去の値動きの激しさを示しています。英語圏でもそのまま通じる、標準的な投資用語です。
計算の考え方と期間の違い
基本は「日次の標準偏差×√年数」
HVは、株価の「日次リターン」の標準偏差に√252(営業日ベース)を掛けて年率換算したものです。期間は5日、20日、60日、90日などがあります。短期は感度が高く、長期は平均化されてブレが小さくなります。短期トレードなら20日、長期なら60〜90日が一般的です。
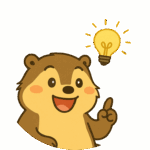 えりちゃんす
えりちゃんすこちらの記事で標準偏差について説明しているよ
ボリンジャーバンドとは?
HVが高い銘柄=ハイリスク?
価格が荒れやすい=損益のブレも大きい
HVが高い=投資チャンス?と思われがちですが、必ずしもそうとは限りません。高ボラ銘柄は損も得も大きくなる可能性があり、初心者には精神的にもハードです。NISA口座で長期保有するなら、安定感のある低ボラ銘柄の方が相性が良いケースもあります。
実際の銘柄でHVを見てみよう。


例:レーザーテック vs 花王
例えば、レーザーテック(6920)の20日HVはしばしば60%を超える一方、花王(4452)は20%台と穏やか。
どちらが正解という話ではなく、「あなたのリスク許容度」に合った方を選ぶ判断材料にできます。
クリックして大きくしてみて下さい。HVと書いたレンジのところです。
どこでHVを確認できる?
TradingViewや証券会社ツールで簡単に。
TradingViewは無料アプリとして使えます。私もNYダウの動きを追いたい時はこちらでみています。
証券会社のアプリでは筆者一押しの松井証券の日本株アプリ。
銘柄を比較する上で、定期的にチェックする習慣をつけましょう。
ヒストリカル・ボラティリティの目安
この表は20日間の値動きから年率換算した数値です。
| HV(年率換算) | 値動きの激しさ | 投資判断の目安 |
|---|---|---|
| 10〜20% | 非常に安定 | 長期保有向き。ディフェンシブ銘柄に多い(例:花王など) |
| 20〜40% | 普通〜やや高め | 日本株の平均的水準。個別株の一般的な変動幅 |
| 40〜60% | 高ボラティリティ | ハイテク株・グロース株などに多い。注意が必要 |
| 60%以上 | 超・高ボラティリティ | 短期売買向き。初心者にはハードモード |
HVと他の指標の組み合わせ
出来高やトレンド系と併用しよう
ボラティリティだけでは投資判断は不十分です。例えば、移動平均線で方向性を見たり、出来高で勢いを確認したりすることで、HVの意味がより明確になります。「高ボラで上昇トレンド&出来高増」は強い買いシグナルになることも。
ヒストリカル・ボラティリティは、「どれくらいその株が暴れるか」を見抜く指標です。私は新しい銘柄を見るたび、まずHVをチェックして「この子、気性荒そうだな」と構えるクセがついています。自分の性格や資産形成プランに合った銘柄選びのために、HVをぜひ使いこなしてみてください!
他の用語も解説しています
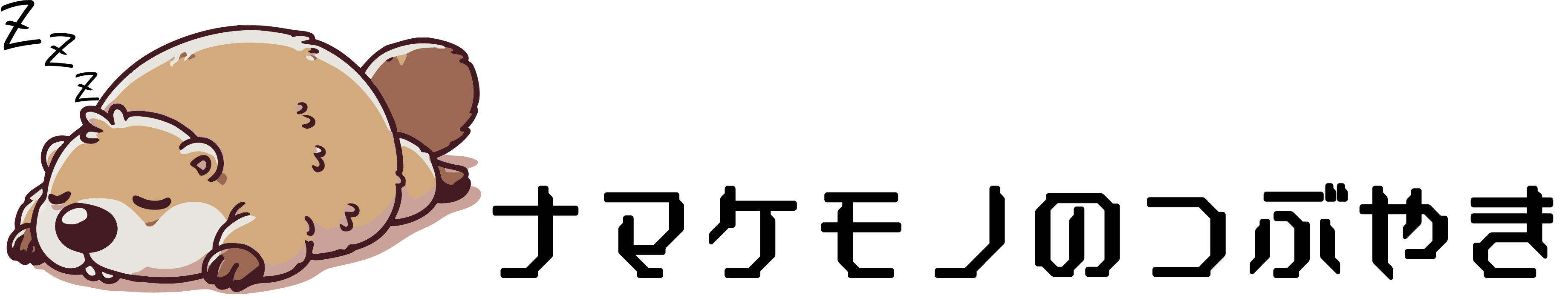









コメント